
型 – パート3 – 和
型 – パート3 – 和
型 – パート3 – 和
古来より日本の型文化の核心は「和」の促進と維持でした。
個人の行動はもちろんのこと、公私を問わず、すべての人間関係は、日本社会に置いて、適度な劣等感の中で厳密に管理された調和の上に成り立っており、それは今日まで続いています。
私たちの「タテ社会」へようこそ。
日本に古来から独自の憲法があったことはご存知でしょう。

この独自の憲法は、精神的な意味で、今でも日本において機能しているものです。この体質は、日本社会の迷宮の梯子の上あるようなものですが、日本の日常生活の中で、形や秩序、過程を経て、日本人に染み付いているのです。
昔々、起源7世紀のあるところに、推古皇后の摂政を務めた聖徳太子という日本人なら誰でも知っている歴史的人物がいました。その聖徳太子が日本人の理想的な美徳を成文化したのが、日本初の憲法です。
日本国憲法の第一条は「和」を基本とし、その後のすべての条文の基礎としました。

さらに、この憲法の17条は、その後の日本文化の発展の基礎となりましました。
因みに、日本の元々の名は「大和」であるので「大きな和」を意味します。
だからこそ、日本国憲法には「和」を建国の理念として体現しているのではないでしょうか。
興味深いことに、この憲法の17番目にして最後の戒めは “大事なことは決して一人で決めてはならない。というのです。
この社会思考のルーツはどこから来ているのでしょうか。
確かに、調和を保つという考え方は、憲法で義務付けられているだけでなく、日本人が稲作農家として、土地との歴史的な人間関係から発展したものなのです。
複雑な灌漑システムを維持するために必要な協力は、精神だけでなく、調和をも必要としたのです。
さらに、集団の和を脅かすものは常に死活問題として捉え、集団の和を守り、維持するために必要なことは何でも行うのです。
そして日本人は親と子、兄弟、上司と部下、大名と家来、そして最終的には天皇陛下と国全体の関係を厳格に規定していました。
これらの関係はすべて型によって定型化されており、それぞれが自分の居場所を知り、定められた形と秩序を守ることによって、正しく機能していると考えられていました。
これらの厳格な規範の上に、正直さ、誠実さ、善意、信頼、自信、無私の心を示すことが求められていました。
また、日本人が社会の中で自分の立場に応じて必要とされる行動様式の型や、各個人の行動を支配するルールに従うことを奨励したり、強制したりするように作られた他の文化的要因もあるでしょう。
型に関連するこの概念の中で最も重要なものは、義務を意味する「義理」という言葉で表現されています。

それぞれの人が他の人に負っている特定の義務があります。その関係は義理の原則を用いて維持されるべきであり、これは型に具現化されていると言えます。
過去のポッドキャストでは、「エピソード4・恩返し」と題して、義理について詳しく説明していますのでお聞き下さい。
日本人がどのように型の上に形成された社会に組み込まれているかについては、今日でも羞恥心という概念が非常に重要な要素であり、日本社会において、常に意識しておく必要があります。

言うまでもなく、自分の家族に恥をかかせることを避け、ましてや他人に恥をかかせることは、何としても避けなければならないのです。
しかし基本的に、ほとんどの日本人は、階級分けされた社会関係を快く思ってはいません。
日本人が第二次世界大戦の灰の中から立ち上がることができたのは、「和」と「型」に基づいた調和のとれた関係があったからであり、日本を再建し、日本人の尊厳を取り戻すという、一心の決意があったからだと思います。
来週の「型」のパート4では、日本人と私たちの社会について探っていきたいと思います。














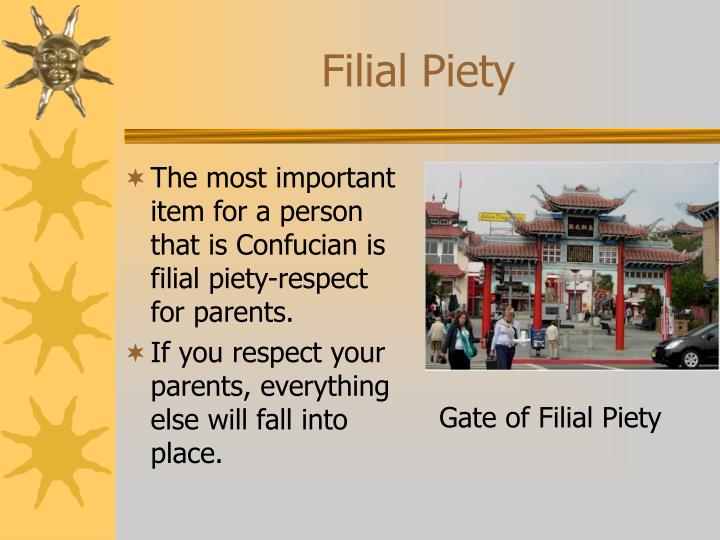



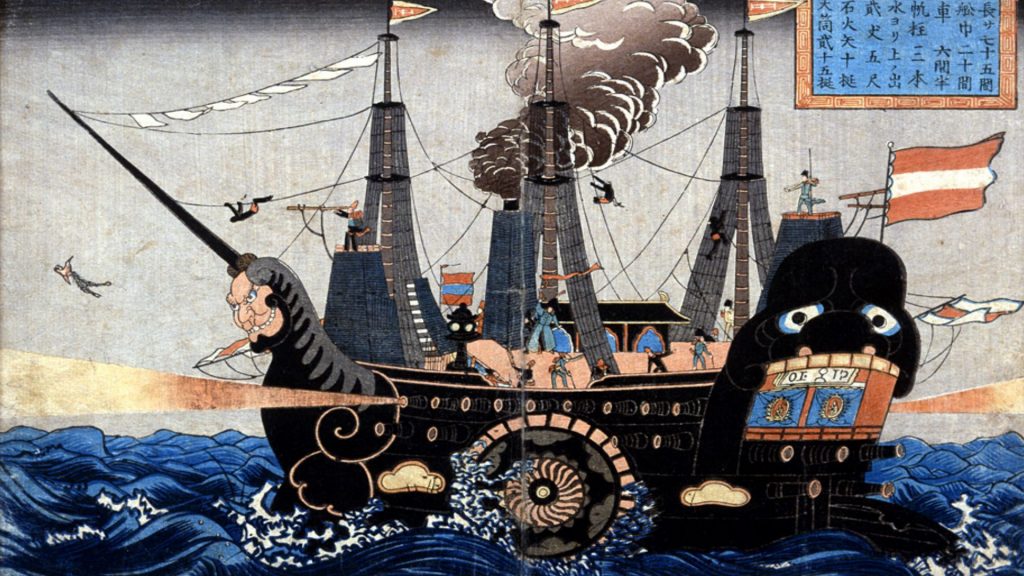








Recent Comments